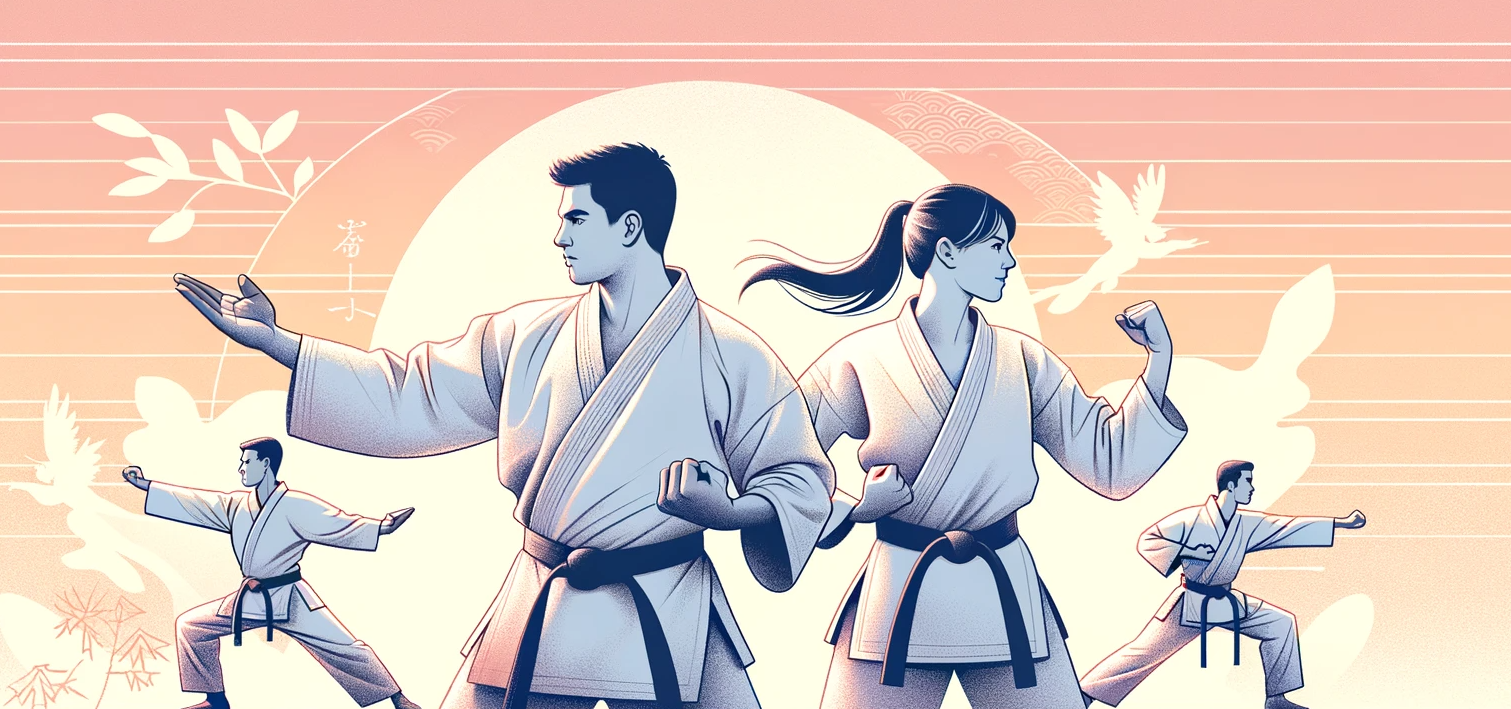
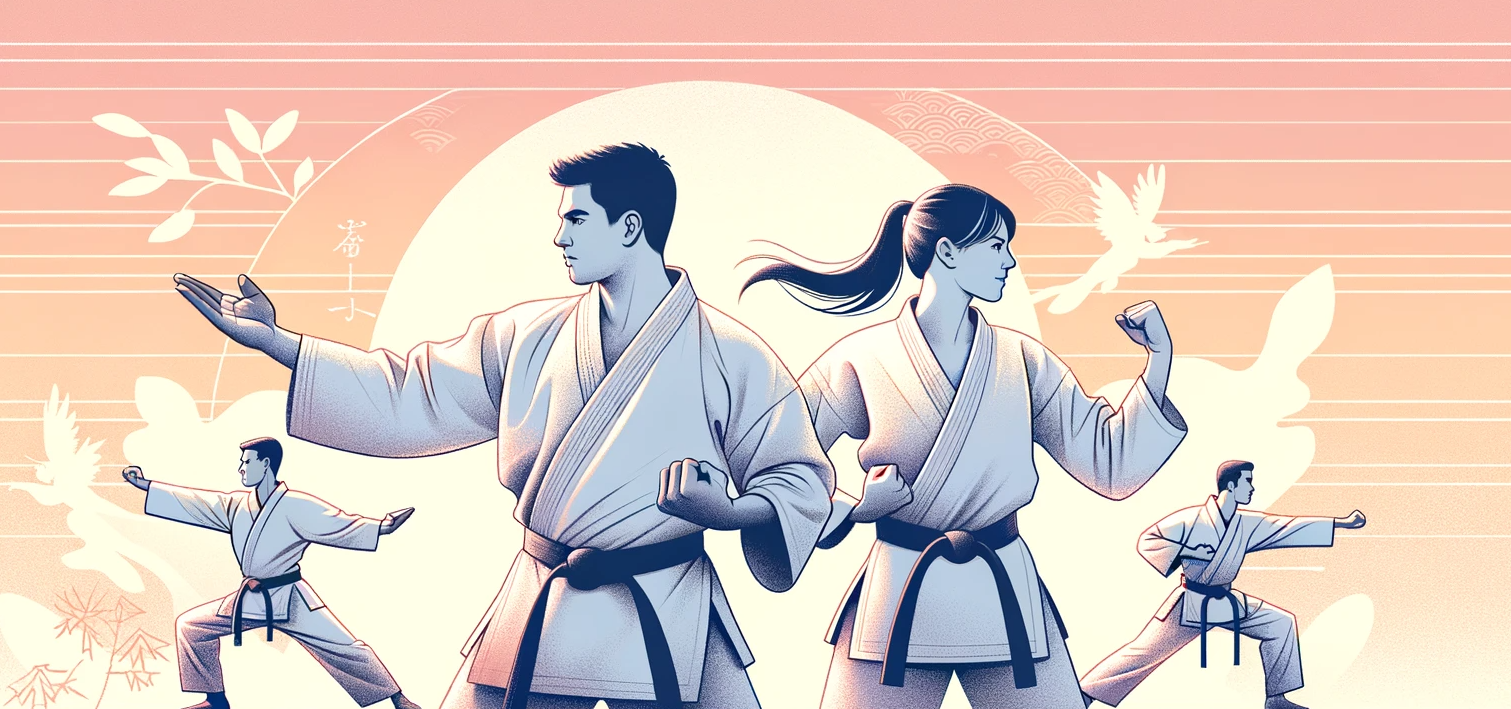
空手の剛柔流の特徴|帯の色や型は?
いわゆる伝統派空手と呼ばれるものには、主に4つの流派があるとされます。このうち、今回は剛柔流(ごうじゅうりゅう)の特徴について説明していきます。級位・段位による帯の色の違いや代表的な型についても学んでいきましょう。
剛柔流(ごうじゅうりゅう)の開祖
剛柔流は沖縄県出身の空手家宮城長順(みやぎ ちょうじゅん)さんが開祖です。宮城さんは沖縄県那覇市に生まれて1930年に自らが作った唐手の系統を「剛柔流」と命名しました。
剛柔流の特徴
この流派は開祖の宮城さんが那覇手の祖・東恩納 寛量(ひがおんな かんりょう)さんから学んだ那覇手に独自の研究を加えることが生まれました。
流派の特徴としては守りの面が強いということが挙げられます。攻撃のための突きや蹴りよりも守りのための払いや受けが訓練の主流になります。
攻撃が主流の松涛館流は遠距離からの攻撃が特徴的なのに対し、剛柔流は近距離から手で捌いたり打ったりする動作が特徴的です。特に「ムチミ」と呼ばれる接近戦は大きな特色となっています。
剛柔流の帯の色分け
剛柔流における帯の色と級位・段位の関係は以下のとおりです。
- 白帯:7級〜9級または無級
- 緑帯:4級〜6級
- 茶帯:1級〜3級
- 黒帯:初段〜
初心者が白帯で有段者が黒帯というのは他の流派と同様ですが、細かな点ではやや違いがあるようですね。
剛柔流の型
剛柔流の型は大きく分けて「基本型」「開手型」「閉手型」に分かれています。一番初めに習う撃砕(ゲキサイ)第二または弐段、剛柔流の背骨ともいえるサンチン(三戦)、ほとんどが受けで構成される剛柔流ならではのテンショウ(転掌)などなど様々な型があり、非常に奥が深いです。
三戦(サンチン)
剛柔流空手において基本中の基本とされる型です。両足のかかとを開いて八の字にして、片方を足ひとつ分前に出します。両手の拳は肩の高さで揃え、脇とお尻をしっかりと締めるのがポイントです。
撃砕(ゲキサイ)
剛柔流の基本とされる型で、撃砕第一と撃砕第二の2通りがあります。他流派の基本形である平安(ピンアン、ヘイアン)とはまったく異なるのが特徴です。盛り込まれている技が多彩で見ている人をグッと引き込む力があります。
転掌(テンショウ)
転掌とは、弧を描くような受け動作で相手の攻撃を無効にしてしまう型です。全体が流れるような動きを取ることから、基本型の柔の型とも呼ばれています。
今回は伝統派空手のひとつ、剛柔流の特徴について解説しました。那覇手の影響を現在に色濃く受け継ぐ剛柔流の魅力にますます惹かれたという方も多いのではないでしょうか。今回の記事をきっかけに他の流派についても興味を持っていただけたら幸いです。
